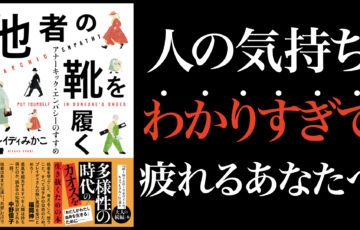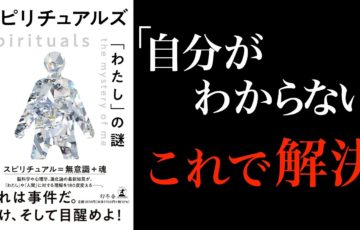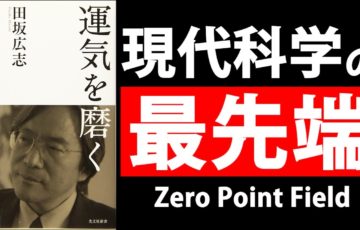このまえ坂爪さんのヤバすぎるブログのまとめ記事、坂爪さんがシェアしてくれてものすごい数の方々に読んでいただけました。坂爪さん、みなさん本当にありがとうございました。
世界をリフレーミングする坂爪圭吾のヤバすぎるブログ9選をくらって、自由になれ。
Facebook(KeigoSakatsume)
https://www.facebook.com/keigosakatsume
twitter
https://twitter.com/KeigoSakatsume
坂爪さんのブログは子育てにも効きますので紹介します。
特に、子育て中の20〜30代のお父さんお母さんに是非読んでもらい、一緒に考えたいなという気持ちでまとめてみました。

スポンサードリンク
親はその尊い想いを押しつける生き物
親は子どもの成長を願い、子どもがたくましく立派に生きていくことを願います。
これは子どもがいるお父さんお母さんなら共感してもらえるんじゃないかなと。
この気持ちはとても尊く素晴らしいものだし、だからこそ親なんだとぼくは思います。
そこに間違いはない。
ですが、ぼくたち親にはこれまでの経験と手に入れてきた「常識」や「価値観」でしか子どもの将来をはかったり見通したりすることができません。
いまの時代がどんなんなっていようと、自分が親の敷いたレールの上を走る列車に乗ってきて、勉強して大学を出て、大きな会社に入ることで安定を得ている(と信じている)人間で、「まあそれなりに、普通に幸せだ」と感じている人なら、疑いなく自分の子どもにも同じような道を歩ませれば同じくらいの幸せを手に入れられるだろうと思い込んでいます。
常識とは思い込み
ところが時代はどんどん変わっていくのです。自分の親の時代と比べてみてください。
まったく違うはずです。
しかもいまは、技術も価値観も変化のスピードが早く、世界も社会も人の気持ちもどんどん変化し移ろいます。
ただ乗っていれば安全だと思っていた列車もそのうちに窓が割れ、屋根が吹っ飛び、外は猛吹雪で、スピードは激速すぎて、下手をすると吹き飛ばされてしまうかもしれません。
そんな時代を生きていくのに、いままで自分に塗りたくられてきたのと同じ「常識」で塗りたくってしまえば、本来人間が持っている「生きる力」が激減し、ただただ心を消耗し、その子の魂が本当に求めているものも絶対に見つけることはできません。
ひとつずつ、思い込みを捨てていく
子どもは自分自身を見つめ直す鏡にもなってくれます。
子育ては気づきです。その「常識」に沿って生きれば、本当に自分が望むものを手に入れられるのか?を考えさせてくれます。
自分の人生も、子どもの人生も豊かにしていくために。
さあ、くらえ。
1.「自分がそれで良いと思ったのなら、それで良い(それこそが良い)」
大前提として「生きているだけでいい」のだと思う。それ以外(金持ちになるとか偉業を達成するとか充実した日々を過ごすとか)はおまけみたいなものだから、何かをやらなくちゃいけないとか、何者かにならなくちゃいけないとかじゃなくて、やりたいようにやればいいのだと思いました。
Posted by 坂爪圭吾 on 2015年6月26日
このブログは会話調になっており、とても臨場感あふれていて面白いので、本文を読んでいただくことを強くおすすめ致します。
坂爪さんが数か月前に東京の渋谷で『はなまるうどんで30人に奢る』っていう企画を(一度に奢った人数の自己ベストを更新する為に)自主開催した時の話。
坂爪「神は『何をしてもいい』と言っているのに、本来であれば何をしてもいいはずなのに、周囲の人たちの反応や態度を気にするあまり、周りのひともそうしているから自分もそうする(周囲から浮かないための行動をとってしまう)ことって、結構ありそうじゃない?」
舞踏家H「あるある!」
坂爪「神は最初から『何をしてもいい』って言っている。かけうどんを頼んでもいいし、かけうどんを頼まなくてもいいし、本当は何をしてもいいんだ。本当は何をしてもいいのに、周囲のひとがそうしているから自分もそうしている(そうさせられている)みたいなことって、結構ありそうじゃない?」
舞踏家H「あるある!」
坂爪「あの時に別の参加者からも面白い話を聞いて、その人はかけうどん(小)を頼んだひとなんだけど、この人が『自分はかけうどん(小)を頼んだんですけれど、ほんとうは300円のうどんを注文したくて、だけど自分が安いうどんを注文すれば坂爪さんに対する負担を減らすことができるというか、そして、そのような遠慮をしている自分に「我慢をしている自分は偉い!」って思って、そうしたんです』って」
坂爪「なんかさ、いまのJAPANは自己犠牲が行き過ぎている感があるよね。あの場においては俺は神(!)で、神は『何をしてもいい』って言っている訳なので、神の望みは『わたしのために安いうどんを注文しなさい』とかじゃなくて、そんなんだったら最初からこんなイベントをやらなきゃいい(最初から人間なんて生まなければいい)訳でしょ?」
坂爪「こういうイベントを開催して、人を呼んでいる時点で、神(坂爪)の望みは『(自己犠牲せよ!なんかではなくて)この空間を楽しんでもらいたい』に尽きるのです。神は、人間に「楽しんで欲しい」と思っている。徹底的に『いまを生きろ』と思っている訳で、自分を犠牲にして欲しいなんて思っていないんだよね」
※誤解のないように書いておきますが、坂爪さんは自分のことを神だとおもって調子づいているのではありません笑。宇宙や世界を開催している神様の縮図として、イベントを開催している自分の立場を「神」とした場合に、という話です。
親は神にはなれませんが、本当は子どもに「楽しんで生きてほしい」と願っているはずです。
なのに、「生きていくには我慢をすることが大切だ」と子どもに教えます。
冷静に考えると自分が異常なことをしてるのがよくわかります。
世界という空間を楽しんで生きることは、はたして我慢をすることで得られるものなのでしょうか?
答えはNO!です。
楽しいことを我慢をさせればさせるほど、「楽しむことは良くないことだ」と刷り込まれ、楽しむことに罪悪感を覚えるようになります。
そして、「我慢をすることがいきていくということだ」と勘違いし始める。そうやって、周りを同じ常識で染めようとし、将来出会うであろう自分の大切な人にも、その「常識」を塗りたくろうとするのです。
自分がやられていると、生きていく上でもっとも重要視すべき「楽しんで生きる」ということを教えることができません。
この記事は、そんな自分と向き合うキッカケを与えてくれます。
2.「他人に迷惑をかけてはいけない」という嘘。
「自分のことは自分でやれて一人前(誰かに頼るのは半人前)」という価値観のままでは、永遠に「誰かに助けを求める力(お互いに助け合う力)」を養うことができない。自分ひとりで問題を抱えてしまうと、鬱病や円形脱毛症や自律神経失調症になったり、最悪の…
Posted by 坂爪圭吾 on 2015年6月24日
この記事は、坂爪さんにインスパイアされたロンドン在住の女性から送られてきたメールを転載したものがベースになっています。
個人主義意識の強い現代において、自分をオープンにしていくことの重要性に気づかされる素晴らしい記事。
「他人から施しを受けるのは惨めなことではなく、寧ろ崇高な経験になる」「実は、皆が何かを誰かに与えたいと思っている」「意識ではなく身体がボスだ」「すべてを受け取ることを自分に許しなさい」など、大量の箴言(しんげん)が含まれている。
そして、私は「他人に迷惑をかけてはいけない」という日本的な教育が、どこまで真実なのかが分からなくなった。過去記事でも書いたように、自分ひとりで出来て一人前(誰かに頼るのは半人前)という価値観のままでは、永遠に『誰かに助けを求める力(お互いに助け合う力)』を養うことができない。
お互いに助け合うことの中には、(もちろんそれによって発生するストレスもあるだろうけれど)其処にしか発生し得ない絶対的なよろこびがある。このよろこびは『自分は生かされている』という感覚に尽きる。何もかもを自分の力でやっている(と思い込んでいる)間は、このような感覚を覚えることは絶対にできない。
「自分のことは自分でやれて一人前(誰かに頼るのは半人前)」という価値観のままでは、永遠に「誰かに助けを求める力(お互いに助け合う力)」を養うことはできない。自分ひとりで問題を抱え込んでしまうと、鬱病や円形脱毛症や自律神経失調症になったり、最悪の場合は自殺をしてしまったりする。
必要なのは固体の思考よりも液体の思考であり、「他人に迷惑をかけてはいけない」というガチガチの常識(固体)よりも「どれだけ楽しく迷惑をかけられるか」という比較的POPな視点(液体)だと思う。
たったひとりきりで完璧になろうとするよりも、困ったときはお互い様のマインドで、頼るときは頼り、甘えるときは甘え、自分にも出来ることが発生した時は「待ってました!」とばかりに差し出して行こう。
・実は、皆が何かを誰かに与えたいと思っている。
・他人から施しを受けるのは惨めなことではなく、寧ろ崇高な経験になる。
・すべてを受け取ることを自分に許しなさい。
「人に頼らずに生きていけるようになってはじめて一人前だ」と子どもに説教するくせに、実は自分は1人では生きていけてないことに気づかされる記事。いま生きているのは、世界があるからです。いまの世界は、みんなで回しています。たった1人では回りません。
それに、(これは極論かもしれませんが)どんなに強くても、どんなに経済力が高くても、もう「この世に生まれた」という事実が存在する時点で1人では生きていないんです。
なのに、意味もわからず、自分とも向き合わず、べっとりと塗りたくられた「常識」を思考停止状態で自分の子どもにも塗りたくるのです。
子どもに人に頼らずに生きることを刷り込むのではなく、「誰かに助けを求める力(お互いに助け合う力)」を養える経験をプレゼントしたいと思える記事。
3.人生とは、自分を楽しませることである。
自分で「行く」と決めてさえしまえば、(地球の裏側だろうが)何処にでも行くことができる。自分で決めてしまうことの威力は半端なくて、自由だと思った瞬間にその人は自由になるし、不自由だと思った瞬間にその人は不自由になる。大概は『自分が望むような人生になっている』のだと思いました。
Posted by 坂爪圭吾 on 2015年6月12日
坂爪さんが神と崇める、「鈴木さん」という人の話。
<参考記事>【全人類必読】新潟で出会った本当に本当に本当にやばい人の話。 ー 本当は誰だって何だって出来るんだよ ー
自分が熱中できるものに没頭している瞬間は、自分が幸せかどうかなんてことをいちいち考えたりしない。自分を楽しませられていない時に、人間は苛立ち、他人と比較し、未来に不安を覚えたりする。
何をしている時に自分は楽しさを感じるのか、何をしている時に「他には何もいらない」という充足感を覚えることができるのか、それを知ることが『自分を知る』ということなのだろう。
鈴木さんは「自分を楽しませる」天才で、全身から『生きていることがうれしい』というよろこびが溢れている。少年のような輝きを帯びた瞳を一目見るだけで、見ているこちらまで猛烈に嬉しくなってしまうエネルギーに溢れている。
「自分が熱中できるものを見つけて、それに取り組んでいる姿を見せる」ことは、半端ない社会貢献だと思う。
この話はそのまま子育てに直結します。
子どもになにかを伝えたいなら、親や大人は自らの生き方や姿勢や行動でしか伝えられないんだということを、この記事を読んで肝に命じる必要があります。口だけ動かしてても、絶対に子どもは吸収しません。
前の話とかぶりますが、たいていの親は我慢をして辛いけどがんばってる的な姿勢を子どもに誇ります。
「ほらみろ、オレは家族のためにこんなに自分を犠牲にしてがんばってるんだぜ」と。ぼくもそうでした。
これ、最低ですよね。子どもは生きる希望を見失います。
「ああ、生きてくって辛いことなんだな、、、」と。
そうやって親の生き方を見習って、生きるようになります。
もし子どもに楽しんで生きて欲しいと願うのなら、自分が生きることを常に全開で楽しんでいる姿を見せなければならない、ということに気づかせてくれる素晴らしい記事。
子どものためを思うなら、まずは自分のために生きろ、っつーことです。
<参考記事>「子どものために」とか言っちゃっている大人が、まずはじめに確認するべきこと。
4.すべては「生きている実感」を感じるためにある
周囲や社会からは「こころを殺せば楽になれるよ」とずっと言われてきたように感じていて、言いたいことはわかるけれど、それだけは絶対に受け入れることが出来なかった。こころを殺すくらいなら苦しんだり思い悩む道を選ぶと思って生きてきた成れの果てが、いまの自分なんだなと思いました。
Posted by 坂爪圭吾 on 2015年4月16日
どうしても自分の代わりを見つけることができないものがある。それが「自分の気持ちを表現すること」であり、だからわたしはこうして懲りずに文章を書いている。
何かを書くことは「遺言を残す」ことに似ている。これが自分の最後のことばになるとしたら、自分はどのようなことばを残すのだろうか。「自分はどのような人間で、どのような人生を望み、実際にどのような日々を過ごしていたのか」ということは、その人自身が存在していた何よりの証明になる。
何かあたらしいことに挑戦しようとするときに、自分の行動をセーブしてしまう最大の感情は「傷つきたくない」という言葉で表現できる。他人から笑われてしまうことや、周囲の理解を得られないこと、失敗してしまうことなどの痛い目にあうことを通じて「傷つきたくない」と思ってしまうからこそ、次の一歩を踏み出すことに躊躇してしまう。傷つくくらいなら、何もしていない道を選びたくもなる。
しかし、当たり前のことだけれど、すべての瞬間には終わりがある。いつか、傷つくことさえもできなくなる日が、必ず来る。「傷つく」とか「傷つかない」とか、そういうものがすべてどうでもよくなってしまう瞬間が、遅かれ早かれ、誰のもとにも必ず訪れる。
そして死ぬときに思うのだろう。「もっと傷つけばよかった」と。もっと自分を投げ出して生きれば良かったと、成功するとか失敗するとかそういう次元を飛び越えて、自分を投げ出すことで「もっと生きていることを実感したかった」ということを、死ぬ間際に痛烈に感じながら消えていくのだろう。
失敗することも、成功することも、何かに傷つくことも、それを遥かに凌駕するよろこびに触れることも、すべては「生きている実感」を感じるためにあるのだということ。わたしは「生きている限り、生きていたい」と思っている。
自分の気持ちを出さずに協調すること、全体のために自分を犠牲にすることは良いこと、いやむしろ当たり前のことだという風潮がいまの日本にははびこりまくっている気がします。
そしてそれは、子どもの「楽しく生きる」未来を確実にむしばんでいくもの。
そうやって自分を押し殺し、周囲の目を気にして自分が喜ぶこと・楽しいこと・嬉しいことを表現せずに生きるということは、「生きない」という選択だとぼくも思います。
<参考記事>表現しないということは、生きないということ。
・周囲に合わせるのは当然のこと
・他人の目を気にして生きることは大切なこと
この記事の中に書いてある、坂爪さんの”すべては「生きている実感」を感じるためにある”という言葉は、上に書いた「枯れはてた価値観」をぐしゃりと踏みつぶしてくれます。
難しくて大変なことかもしれませんが、傷つくことを恐れず、大人も子どもも自分を表現していこう。
5.「こうでなきゃいけない」なんてことはないんだよ。
学校に行くのが絶対じゃないし、仕事をするのが絶対じゃないし、幸せな家庭を築くことだけが絶対じゃない。幾通りの人生にもそれぞれの味わい深さみたいなものがあって、大事なのは「意味不明な他人と比べないこと」と「(厳しい場合もあるけれど)他人に優しくあろうとすること」だと思いました。
Posted by 坂爪圭吾 on 2015年4月10日
別に暗い話をしたい訳ではないけれど、私は常に「死にたい」と思っていた。学校もつまらず、友達もおらず、何をしていても退屈だと感じていた私にとって、いまいる世界が「生きるに値する」と思うことは大変なことだった。
ただ、自分が好きな音楽を聞いている時間だけは自由になることができた。そのような音楽は「(何もなくても、何もかも失ったとしても)生きていいんだよ」といってくれているような気がしていて、私は、自分が好きなものに触れている時間だけは自由になることができた。
自分を大事にしようとするから、自分が傷つかないように無難な選択ばかりを繰り返し、結果としてほんとうは開きたがっている生命の種を「安全な生活」によって捻り潰してしまう。現代社会は別に本気なんて出さなくても生きていけるからこそ、本気を出せないことが生命の実感を遠ざけている。
— 坂爪圭吾 (@KeigoSakatsume) 2015, 4月 5
生きることには免許も資格も他人の許可も必要ないのに、いつからか「生きるためには免許や資格が必要だ」みたいに思い込まされてしまう瞬間が誰にでもあって、でも、そんな時でさえも、自分の大好きなものは「(何もなくても、何もかも失ったとしても)生きていいんだよ」って言ってくれる。
「こうでなきゃいけないなんてことはないんだよ」と言ってくれるものが、自分には何もないと思っていた自分には、何よりもやさしく響いてきた。余裕がなければ、やさしくなれない。
美しいものに触れたとき、自分が心の底から大好きだと思えるものに触れたとき、ひとは幾つかのことに感動している。
美しさを覚えた対象そのものだけにでなく、美しいと感じることができる「自分の心の存在」にも感動しながら、同時に、いつまでもそれを見ていることができないという事実に胸を締め付けられたりもする。
すべてに終わりの瞬間がある。過去を悔やんだり未来を不安に覚えることもありながら、いつしか、過去を悔やむことさえも、未来を不安に感じることさえもできなくなる日が、必ず来る。
それまでの時間をどのように過ごすのかはひとりひとりの手の中にあって、何が正解だとか、何が間違いだとか、これをしたら誰かがどう思うだろうかとか、そういうものの一切は、すべてが瑣末なものになる。
生きているのはいまだけだということ。
そうなのだ。これなのだ!(書きながら興奮状態笑。)
本当は生きているだけで素晴らしい。美しいものに出会えたことや心から好きなものに出会えたら、それはもう最高に最高すぎる状態なハズなのだ。
それなのに世界は、「違う、こうでなければいけない」「そうでなきゃ良くない」「こうやって生きないと意味がない」「意味がない、意味がない、意味がない、、、」などとぼくたちにナイフを突きつけながらせまってくる。
そしてそうやって、自分の子どもにも、自分にも、自分でナイフを突きつけるようになる。
本当は大好きな人が楽しんでいるのが嬉しいはずなのに。
子どもが喜びを感じること、子どもが純粋に楽しんでいることに、親や大人が意味を後づけするなんて腐っている。
むしろ一緒に喜び純粋に楽しむことが、「本当の子育て」ではないかと思いました。
まとめ
原点に戻ります。
子どもがこの世にあふれんばかりの命を解放して叫んだ瞬間、あなたはどんな気持ちになりましたか?
その時の感情が、答えだと思います。
わが子は、生きているだけで尊いハズです。
生きていることを感じ、臆することなく自分らしさを表現し、人生をめいっぱい楽しんでくれればそれでいいハズです。
なにかをやる「意味」とか「常識」とかそんなもん本当はいらないんです。
余計な「常識」で子どもの心を覆い隠したり重荷を背負わせたりするのはやめにして、一緒に人生を楽しむ仲間として同じ時間を過ごせれば最高ですね。
人生は続く。
それではー!