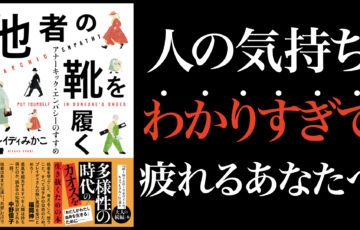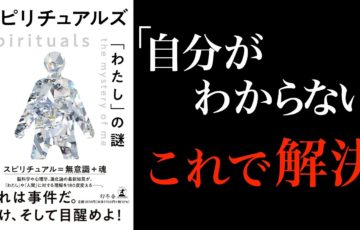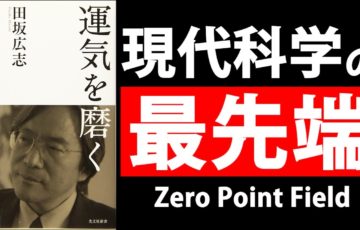TED Talksから。
これはとても刺激的なプレゼンテーション!だったのでご紹介。
Beau Lotto & Amy O’Toole
Sience is for everyone, kids included
ボー・ロット&エイミー・オトゥール 「みんなの科学(子供も大歓迎!)」
まず始めに、書いてある通りに読むゲームということで、会場の人達にスクリーンの文章を声に出して読んでみてー!と。
W at ar ou rea in ?
会場からは一斉に
What are you reading?
の声。
ほとんどの人は、知覚が経験に依存しているからこうなる。脳が無意味な情報に意味を見いだす。
つまり、現実を見ずに過去に役に立ったことだけを見ていると、ボー先生は言います。
ここから先はほぼそのまま書き取ったものです。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
科学とは「生き方」実験は「遊び」なら子供は科学者だ!という仮説
知覚は、人間の思考や知識、信念、希望、夢、服装、恋愛などすべての基本であり、それが経験に依存するなら人間は同じことを繰り返すだけ。これは大問題。それじゃ新しい見方ができない。じゃあ見方を変えるにはどうする?新しい見方は必ず疑問を持つことから始まり、そこから不確定要素が生じる。
新しいことをするにはそこに踏み込まないといけない。
どうすればいいか?人類の進化から答えは出ていて、そのやり方ならどんな難問にも立ち向かえます。既成概念を疑うということです。不確実性の高い発想は、生命や宇宙に関する疑問よりもはるかに未知の領域なんです。その立ち向かい方というのは「遊び」であり、それは「方法」というより「生き方」だと専門家は言います。遊びは不確定要素が好まれる数少ない営みの一つです。柔軟性・発展性があり、共同作業であり、人間関係を育む。
また、遊びはその行為自体がご褒美みたいなものです。
これらの性質は優れた科学者になるための条件と全く同じ。
●celebrate uncertainly
●adaptable to change
●open to possibility
●cooperative
●intrinsically motivated
どんな創作活動でもそうですが、科学だって「生き方」なんですよ。
で、遊びにルールを設けるとゲームになる。それが「実験」です。
じゃあ科学が「生き方」で、実験が「遊び」だとしたら、誰だって科学者になれるのでは?
そこで遊びの天才である8〜10歳児、25人に手伝ってもらい、彼らの学校でハチの研究を行いました。
これは、子供の科学に対する意識や自意識を変えるのが目的です。
ステップ1「疑問を持つこと」
ちなみに助成金はもらえませんでした。科学者や教育関係者は皆「子供にはムリだ」と。
だけどやっちゃいました。
子供たちからでた疑問の中の5つはここ5〜15年の科学誌の方向性と一致してました。
プロの科学者と同じ疑問を抱いたんです。
[12歳の科学者でTED最年少スピーカーとなったエイミーから、子供たちが抱いた疑問についての説明]
人間とサルは見た目が似ているから思考パターンも似てて当然。でも他の生き物はどうなんだろう?見た目が全然違う人間とハチの思考が似ていたら面白い。ハチが人間みたいに賢いってことある?条件や法則を学んで変化に適応する能力がハチにある?脳細胞が100万個しかないハチが人間と似ていたらスゴイ。でもハチにはいい花を見つける力がありますよね。時間や明るさや天気や見る方向など関係なしに。
ステップ2「実験の設計」
つまりゲーム作り。子供達が自らゲームを考えだしました。
[こちらもエイミーより]
ハチにパズルをやらせて、ハチが色を見分け、さらに色の配列を理解できるか試したんです。青に囲まれた黄色のところに行ったらご褒美をあげる。
黄色に囲まれた青もオッケー。解き方はいろいろあるけどハチはどう考える?楽しい実験でした。大人だってこれがうまくいくかわからなかったから。
先生たちも戸惑ったでしょうね。科学者と違って知らないことをやるのに抵抗がありますから。
ステップ3「観察」
データを集め、平均値を出したり、そして論文を書いて学術雑誌に投稿。
論文は序論・研究方法・結果・考察。
序論=疑問とその理由,方法=何をしたか,結果=データ,考察=テキトーに
それが科学論文。笑
で、僕(ボー先生)が子供達の発言を彼らの口調でまとめました。
筆頭著者は学校名で、冒頭に多数の著名者の名前、つまりほとんど8〜10歳の子供達の名前を。
それをオンラインの学術雑誌に投稿したら、「いろいろな意味で一次審査不合格」と言われたが、米国科学アカデミー会員の著名な神経科学者に見せると、「なんと斬新な論文!広く読まれるべきだ」と。視覚の研究者には「大人だったら掲載される」と評価され、再度投稿したけどやっぱりダメ。
で、その研究者とさらに別の学者に解説を書いてもらい、推薦してもらう形で生物学誌に投稿したら5人に査読され、そして掲載。
実験期間は4ヶ月で発表するのに2年かかった!
人間は普段受け身ですが、知らないことに挑戦して、目を開けると物の見方が変わる。
遊びながら未知の領域に入る機会をくれる。それが科学です。
科学教育で大切なのは誰でも自由に発言できることだと思うので、最後はぜひエイミーのほうから。
[エイミーより]
何かを発見する行為は楽しかったし、よくわかったのは誰にだってできるってことと、小さな疑問が大発見につながること。
世の中にはすぐに考えを変えられる人も逆の人もいますけど、私はすぐに科学を好きになれた。
実験をやっていたら、科学の面白さがわかったんです。
そして機会さえあれば誰でも何か発見できる。
私にとってこれがその機会でした。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
論文の最後にこう書いてあったそうです。
We like bees.Sience is cool and fun because you get to do stuff that no one has ever done before.
私たちはハチが好き。科学はカッコいい。そして楽しい。なぜなら、今まで誰もやったことがないことができるから。
原点は、今までやったことのないことができたという喜びなのかもしれないですね。
1月14日放送 | これまでの放送 | スーパープレゼンテーション|Eテレ NHKオンライン
「みんなの科学(子供も大歓迎!)」 …
上のサイト、NHKのスーパープレゼンテーションという番組の、伊藤譲一さんの解説にはこう書いてあります。
子供の遊び、子供の質問というのは、科学の研究のプロセスによく似ているということ。
だけど大人になるにつれて、遊んだり、質問したりしなくなっていく。
「分からないもの」に直面したとき、仮説を立てて実験をし失敗もして学びを得るという科学の研究プロセスが必要になる。
そして、実験をしながら自分で体験をするというのは強い学びになる。
子どものように自由に発想し、遊びながら実験するという環境を守っていくこと。
つまり子供のまま、大人になるという環境を作ることが大切だということです。
それこそが大人の役目であると肝に命じて子育てに向き合おう。
こういう話を聞くと本当に勉強になる。
子育ては、自分が失ってきたものに気づくことであり、失ったものを子どもには失わせない、というとても奥深いものだと感じました。
それでは!