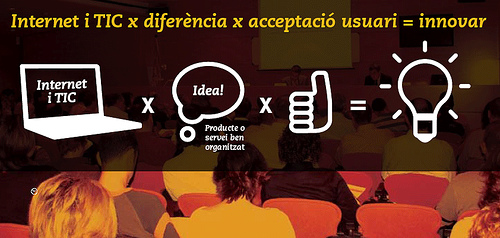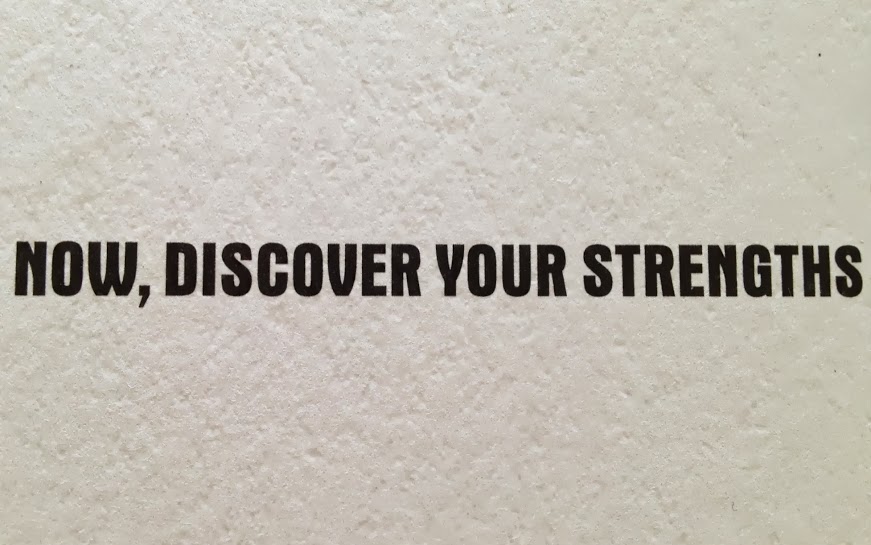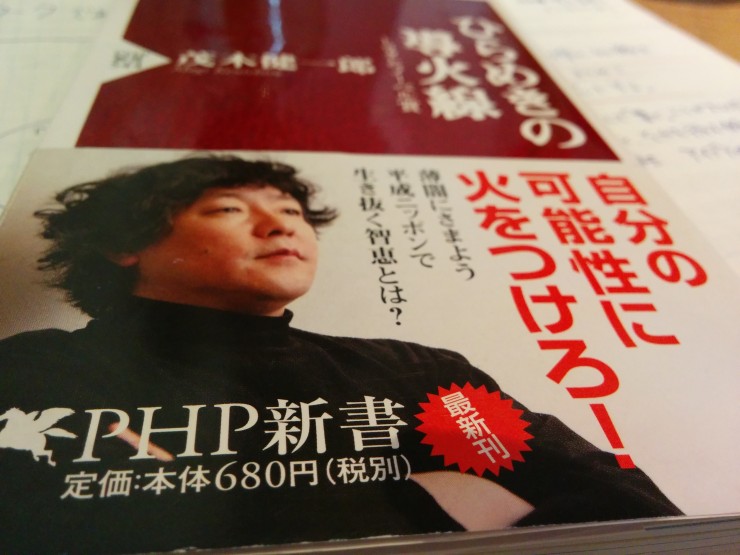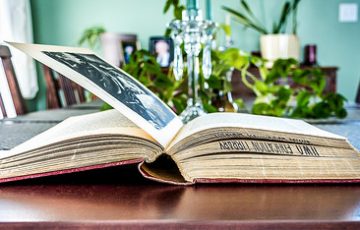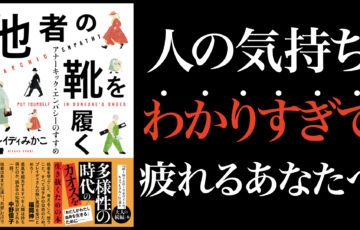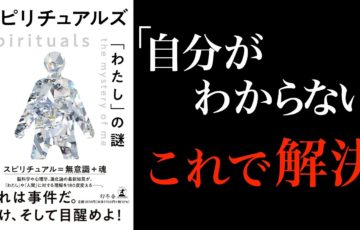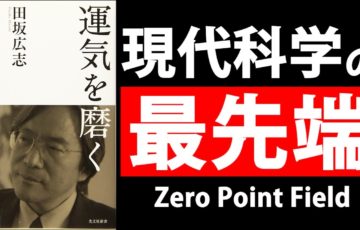私はこれから、会社の内部に向けてのブランディング活動「インナーブランディング」活動に取り組もうとしているところです。インナーブランディングとは、文字通り、会社の内部つまり従業員がブランドについて意識し、顧客と約束するブランド経験を提供をしていくためにどんなことを大切にするか、というのを広めていく活動です。
そのインナーブランディング活動には、人と人、打ち手と打ち手がつながるような分かりやすい「ストーリー」が必要になるだろう、というのが最近浮かんでいるイメージです。そこで今、戦略とストーリーの勉強のために会社の先輩に貸してもらったこの本を読んでいます。
スポンサードリンク
まだ読みはじめたばかりです。
最近の私の本の読み方は、「目次をみて気になるところだけ読む」というスタイルにしていたのですが、この本はその尊敬している先輩が強く進めてくれているのと、著者が本の中でしきりに「すべて読まなければストーリーがわからないから是非通して読んでくれ」と言っているものですから、結構な分厚さの本ですが、がんばって全部読んでみようと思います。
この本では、題名とおり「競争の戦略」が、ストーリー仕立てで理論的に説明されています。どんなことが書かれているかというと、
現在多くの企業で作られている「戦略」は、戦略全体に動きがない、やるべきことリストを箇条書きにした「静止画」がほとんどであるが、戦略とは、それを構成するさまざまな打ち手が「ストーリー」としてつながっていて、ゴールに向かって動いていくイメージが「動画」のように見えるものである。
というようなことを言っていて、なにより(以下は引用)
戦略に関わる社内外の人々を面白がらせ、興奮させ、彼らを突き動かす力を持っていることが戦略が成功するための絶対条件であり、さらに言えば戦略を作っている人自身がストーリーに興奮し、面白がり、実に楽しそうに戦略を話してくれる。
と言っています。
戦略とは、個々の打ち手や1人ひとりのつながりであり、それら1つ1つのつながりにより出来上がっている「ストーリー」のことであり、
打ち手や1人ひとりが自然につながり、流れ、動いていなければ、そこには何らかの本質的な矛盾や欠陥がある
と著者は言っています。
ではなぜストーリーが必要なのか?それには3つの理由があります。
1.ストーリーになっていると面白くて、記憶に残りやすい
脳科学的に言うと、右脳の「感覚」「新奇性」と左脳の「理論」「慣例」の連続したパス回しがループすると、「面白い!」という感覚につながるようです。
戦略を考えるときはきっと、みんなが「それいいね!」という「感覚」を持つような目指したい場所にたどり着くためには、どのようにして、何をすれば達成できるか、というのを「理論」に落とし込んで、その先でまた違った打ち手とのつながりを発見(つまり「新奇性」)し、つながりを感じながら成功する姿をイメージして、、、というような右脳と左脳のパスのサイクルが回るために、刺激的で面白いと感じるのだと思います。
また、ストーリーは頭の中で動画を再生しているようにイメージが浮かぶもののため、やはり面白いし、なにより人々の記憶に残りやすいということがあると思います。
2.面白いストーリーは人に語りたくなる
面白いストーリーが出来上がると、伝えたくなります。人は自分が知っている面白いことを誰かに伝えたがるようです。つまり面白いストーリーは波紋のように、かつ自然な形で、伝えたい人にどんどん伝わっていく。
戦略は1人では実行できませんから、たくさんの人を巻き込む力が必要です。面白いストーリーができてしまえば、それは意図せずとも勝手に自然に広がって、たくさんの人を巻き込み、大きなエネルギーが作られていくのです。
3.価値分化という日本の会社の特性
欧米は「機能分化」の社会であり、例えばマーケティング担当は自分の仕事を説明するときに「私はマーケティングのスペシャリストです」と、コミットメントは完全に自分の機能専門性のみに向けられるそうです。機能を組織にインプットするという考え方。
一方、日本は「価値分化」の社会と言われ、例えばマーケティング担当は欧米と違ってこういうそうです。「私はオーディオ製品をやっています。オーディオ屋です。」
日本人は、顧客がどのように使うのか?どのように喜ぶのか?という観点で、組織が外部の顧客に提供する製品なりサービスで自分の仕事や組織での存在理由を定義する傾向が強いそうです。
欧米人が機能分化的で、企業に属している個々はつながりをあまり重視しないのに対して、日本人は自分の組織が顧客に対して与えている価値を考える、つまり内部も外部もつながりを重視している、ということです。
つまり日本人は、つながりのあるストーリーを好むということ。
戦略ストーリを組織の人々で広く共有することの必要性や効果が日本の社会ではずっと大きくなる。
というのが著者が論じているストーリーの必要性です。
今私が取り組んでいるキッズコーチングでも、子どもの記憶に残すためには「イメージング」という手法が必要で、それは映像が思い浮かぶようなストーリーが大切!とおっしゃっていました。「ストーリー作り」は色々なものをつなぐ考え方になり得ます。「ストーリー作り」という視点と方法をモノにできれば人生が変わる気がします。
練習のために、まずは自分や家族の人生のストーリーについて考えてみるのがいいかもしれませんね。
それでは!